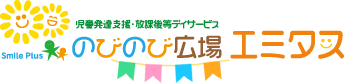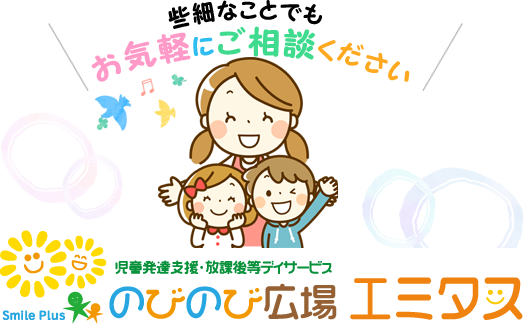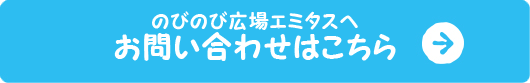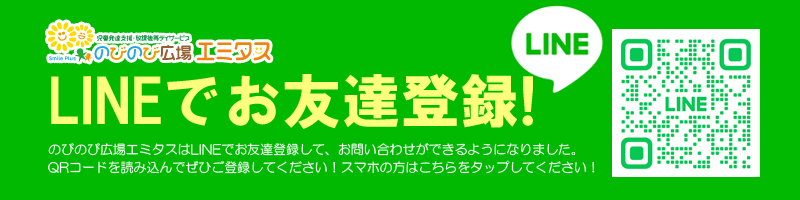番外編:江戸時代の子どもたちの遊び
25.08.28

江戸時代の子どもたちの遊びを
紹介したいと思います。
1. 凧あげ(たこあげ)
江戸時代の子どもたちは、お正月や
お祭りで凧あげを楽しみました。
大きなものでは大人も一緒に参加し、
凧合戦のように空で競い合う遊びも
ありました。
👉 風の力を利用するため、
科学的な学びにもつながります。
2. 独楽回し(こままわし)
木や竹で作った独楽を回して遊びました。
技を競い合うのが人気で、江戸の子どもたち
の「遊びの王様」ともいえる存在でした。
👉 力の加え方や回転の仕組みが分かる遊びです。
3. 鬼ごっこ・かくれんぼ
江戸の町中でも広く遊ばれていました。
現代の子どもたちと同じく、
走ったり隠れたりすることで、
体を思い切り動かす遊びです。
4. はないちもんめ
子どもたちが歌を歌いながら行う集団遊び。
江戸の子どもたちも、手をつないで歌い、
遊びを楽しんでいました。
👉 協調性やリズム感を育む遊びです。
5. 貝合わせ・石遊び
海や川で拾った貝や石を使って遊ぶ、
自然の中の遊びも盛んでした。
石けりや貝殻を使った簡単な遊びは、
今も形を変えて残っています。
江戸時代の遊びは、特別なおもちゃを
買わなくても、身近な自然や道具を
工夫して楽しむのが特徴です。
👉 「限られたもので工夫する」姿勢は、
子どもの 創造力や発想力 を育てるうえで
大切なヒントになります。
関連記事
-
2024.02.28 2月28日(水)カレンダー作り
-
2022.01.07 1月7日(金)七草粥
-
2023.10.20 10月19日(木)公園外出
-
2022.01.12 1月12日(水)かるた 凧揚げ
-
2022.03.01 3月1日(火) カレンダー作り
-
2023.09.15 9月15日(金)カードゲーム