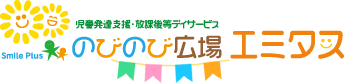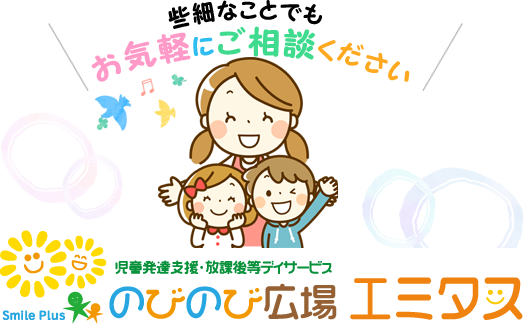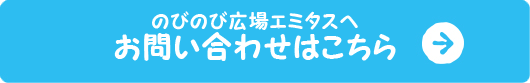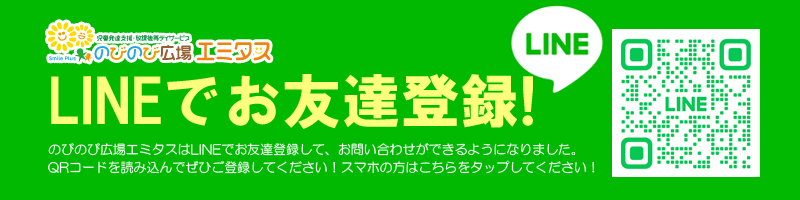脳幹の役割と発達障害の関係

子どもの成長を支える
仕組みとは
こんにちは。
のびのび広場エミタス代表の山口です。
川越市で児童発達支援・
放課後等デイサービス
を行う中で、日々さまざまな
お子さまと関わっています。
脳幹は子どもの発達を
支える“土台”
呼吸や心拍などの生命維持から、
姿勢や無意識の動きまでを担う 脳幹。
この部分は、子どもの成長にとって
非常に大切な役割を果たしています。
特に発達障害を持つ子どもたちにとって、
脳幹の働きは学習や生活を支える
うえで大きな意味を持ちます。
今回は、脳幹の基本的な役割と
発達障害との関係について解説します。
1. 脳幹とは?
脳幹は、延髄・橋・中脳から構成される、
脳の中で最も古い部分です。
-
呼吸・心拍・血圧・体温の調整
-
姿勢の保持
-
反射的な運動のコントロール
といった 基本的な生命活動と
無意識の動き を司っています。
2. 脳幹と発達の流れ
脳の発達は「下から上、内から外」へと進みます。
-
最初に 脳幹 が発達
-
次に 大脳辺縁系(感情や記憶)
-
最後に 大脳新皮質(思考・判断・計画)
脳幹がしっかり機能してこそ、
大脳新皮質の発達がスムーズ
に進みます。
赤ちゃんの時期は、脳幹が体の動きや
反射をコントロールしており、
この段階を経て「意図的な動き」が
できるようになります。
3. 発達障害と脳幹の関係
(1)原始反射の統合
赤ちゃんは生まれたときに
原始反射 を持っています。
成長とともに統合され、
意図的な動き(随意運動)に
移行します。
しかし発達障害があると、
この反射が統合されず、
-
突然の音で驚きすぎる(モロー反射の残存)
-
姿勢や動作がぎこちない
といった形で生活に影響することがあります。
(2)姿勢とバランス
脳幹は姿勢とバランスを整える
役割も担っています。
発達障害や運動障害がある場合、
-
座る・歩くの安定が難しい
-
バランスが崩れやすい
といった困難さにつながります。
(3)自律神経への影響
脳幹は自律神経系も司っています。
発達障害を持つ子どもでは、
この働きが不安定になることで、
-
強い不安や緊張
-
感情のコントロールの難しさ
が現れることがあります。
4. 脳幹をサポートする方法
発達障害を持つ子どもたちが体を
コントロールできるようになるた
めには、以下のような支援が有効です。
-
姿勢保持のための運動(バランスボール、体幹トレーニング)
-
反射統合を促す遊び(ハイハイ、揺れ遊び)
-
感覚統合
これらは 脳幹の機能を助け、大脳新皮質の
発達を後押しする土台 となります。
脳幹の理解が子どもの
成長を支える
脳幹は、生命維持から姿勢・反射まで、
子どもの成長を支える大切な部分です。
発達障害のある子どもにとっては、
この脳幹の発達が支援されることで、
姿勢や動作が安定し、学習や生活の
基盤が整っていきます。
👉 大人が脳幹の役割を理解し、遊びや
運動を通じて子どもをサポートすることが、
安心した成長につながります。
川越市で児童発達支援・
放課後等デイサービス
をお探しの方へ
のびのび広場エミタスは、埼玉県川越市
でお子さまの発達をサポートしています。
現在、笠幡教室・野田教室で療育を
行っており、的場教室は2025年11月
にオープンします。
遊び・運動・食育を取り入れた療育で、
お子さまが安心して成長できる
環境を整えています。
見学や体験も随時受付中です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
笠幡教室 049-299-7204(池ノ谷)
野田教室 049-256-9743(發知)
的場教室 049-299-7204(川上)
関連記事
-
2021.08.17 8月17日 今日も雨、でも楽しみました。
-
2024.09.02 9月2日(月)避難訓練
-
2022.07.28 7月28日(木)収穫
-
2023.02.02 2月1日(水)公園外出
-
2023.11.22 11月21日(水)野菜ジュース作り
-
2024.02.03 2月3日(土)図書館外出