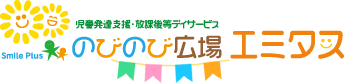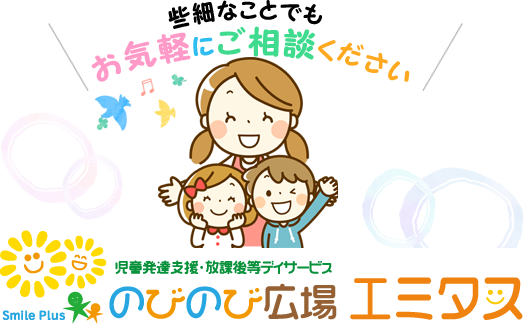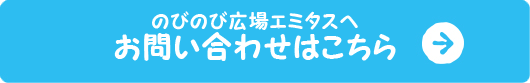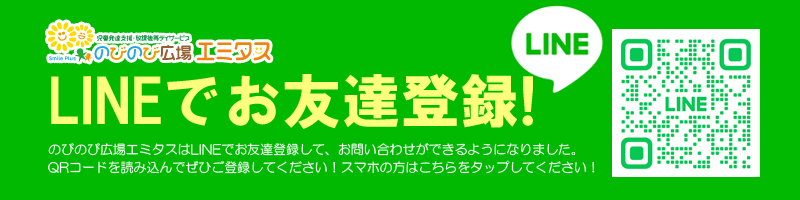ASDの子どもに見られる体の特徴と支援の工夫

自閉スペクトラム症(ASD)の子どもたちは、
コミュニケーションや感覚の特性だけでなく、
「体の使い方」にも特徴が表れることが
あります。
それは単なる「不器用さ」や「姿勢の悪さ」
ではなく、脳や感覚の発達と深く関係している
サインです。
今回は、ASDの子どもに見られる
体の特徴と、それを支えるための具体的な
支援の工夫についてご紹介します。
ASDの子どもに見られる体の特徴
1. 姿勢保持が苦手
猫背になりやすかったり、
座っていても崩れやすいことがあります。
これは筋肉の緊張や体幹の弱さに
関係していることが多いです。
2. 動作のぎこちなさ
走る、ジャンプする、ボールを投げるなどの
動きにスムーズさが欠けることがあります。
協調運動が苦手なため、遊びや運動で
つまずくことも少なくありません。
3. 感覚の影響
-
感覚過敏 → 音や光に反応して体がこわばる
-
感覚鈍麻 → 痛みや疲れを感じにくい
こうした感覚の特徴が体の動きに影響するケースもあります。
4. 体の位置を把握しづらい
「自分の体がどこにあるのか」を
感じにくい子もいます。
これを 固有感覚(プロプリオセプション)
の弱さと呼び、姿勢や運動のぎこちなさに
つながります。
支援の工夫:日常に取り入れられる工夫とは?
1. 動きを真似る遊び
-
ミラーダンス(鏡のように相手の動きを真似する)
-
模倣体操(先生や保護者と一緒に同じ動きをする)
👉 「同じ動きができた!」という達成感が、自信にもつながります。
2. 強さや速さを感じる活動
-
トンネルくぐり
-
押す・引く遊び
-
布団に包まれる体験
👉 感覚に刺激を与えることで、体のコントロール力が高まります。
3. 体の境界を感じやすくする工夫
-
クッションやボールで軽く押される
-
抱きしめられる感覚
-
布で包まれる遊び
👉 「ここまでが自分の体」という感覚が分かりやすくなります。
ASDの子どもたちが見せる「体の特徴」は、
本人が困っているサインでもあります。
それを「できないこと」として
捉えるのではなく、支援のヒント として
活かすことが大切です。
-
遊びを通して体を育てる
-
感覚を整える工夫を取り入れる
-
成功体験を積み重ねる
こうした支援が、子どもの安心感と
自信を育て、生活や学びを支える力になります。
関連記事
-
2024.02.16 2月15日(木)室内活動
-
2023.10.17 10月17日(火)風船バレー
-
2022.10.26 10月25日(火)綱引き大会
-
2024.12.12 12月12日(木)動画鑑賞
-
2022.03.18 3月18日(金)足でじゃんけん大会
-
2024.06.25 6月25日(火)ダンス教室